![]()
![]()
![]() 6.
線としてのアーティキュレーション
6.
線としてのアーティキュレーション
私たちが、自然界の万物の営みを見るとき、
それは時の流れとともにうつろう自然の姿の残像のイメージに、私たちはその何たるかを感じます。
音楽を聞くときもまた、
時の流れの中に描かれて通り過ぎた楽音の響きのイメージが残響となって、その何たるかを感じとります。
残像、残響、これらにおぼえる感動のイメージは、何秒、何十秒かの間になされた美しい「変容の様子」なのです。
ここでは、そのような美しい時間の流れを、連なる音の表現で、どのように演奏するかを考えてみます。
では、前回に続いて、鈴木慎一の「音楽表現法」からの啓示にそって進めます。
今回のテーマは、アーティキュレーションの核心ともいえるでしょう。
4.
線と点と空間について
1)線、すなわちレガートについて
鈴木は、ヴァイオリンやフルートと区別して、ピアノという楽器の問題について特筆しています。
これは、まさしくギターにも当てはまる問題です。
ピアノはハンマーで弦を叩き、ギターは弦をはじくことと、音の自然衰退、そして和声楽器であるところが共通です。
両者とも、管弦楽器ように一様な太さのフレーズの線は描けないわけですが、
アタックのアクセントと、その残響を利用して心理的にレガートな音の線を描いてゆく特別な技法を要する楽器です。
さらに、和声楽器として和声の上下バランスにまで気を使わなければならないので、
彼はそのことも含めて、「メロディを生かし歌う技法」の指導と練習が不可欠であることを強調しています。
つまり、音を出す瞬間以降、表現のためにできることは限られていて、
その限られた技巧には、絶妙な消音、あるいは、次の音の適切なタイミングがあるのみです。
けれど、ギターはピアノに比べれば、音色の変化の面で、技術によっては少なからず多様性があるといえるでしょう。
和音で留意することは、和音にはかならず主となる音があって、すべての音を一様に弾くことはないことです。
単音も和音も、ギターでは「撥弦」と「消音」に、すべてを凝縮しなければならない宿命にあるわけです。
消音(スタッカート、休符)については、次回に続く項の「空間の表現」および「点の表現」で論じられますが、
私たちギタリスト(?)は、消音をどれほど意識しているでしょうか?
とりあえず、レガートからはじめましょう。
鈴木は、各種レガートの帯状の図を描いて、音量において、太くなる線、細くなる線、その変化が曲線的なもの、
あるいは、それらの入り組んだものなど、それらの滑らかな変化のある演奏の難しさを述べています。
これは自明の理で、たとえその線を一様の太さに保つことすら困難なことです。
ギターでは i と m の交互で弾くことが基本と思われがちですが、それに捕らわれず、イエペスがやっていたように、
音質や音量を一定化や、コントロールを容易ににするために、あえて一本指で連続に弾いてもいいわけです。
それに、上声部はすべてアポヤンドでなくてはならないと思う人はいないでしょう。
アポヤンドは思い余ってするもの、と思っていいし、自分の表現意欲が、時にそれを求めるものでもあります。
ギターにおいては、連続する音符をレガートに弾くことは難しいことで、音楽への大きな壁でもあります。
つまり、レガートには、ディナーミク(強弱)のいかんに関わらず、個々の音量コントロールが必至です。
安定した音量を保つには、弦、フレットの場所で音の響き方が違うことも知らなければなりません。
和音をレガートに弾くとなると、さらに難しく、結局左指の俊敏性という容易ならざる問題にもぶち当たります。
ピアノには、指を離しても和音の残響が途切れさせないサステイン・ペダルがありますが、ギターでは、
ポジション移動などで必然的に発生する積極的な消音を効果的に使ってレガートを表現するしかありません。
つまり、和音のノンレガート奏法をマスターしなければなりません。
鈴木は、レガートの中でのアクセントについて、
それは迫力を感じさせる手段であり、コントラストを演出して効果がでることを持論としています。
つまり、アクセントをつける直前の音響状態をどうするかということです。
彼が言うように、アクセントの前には瞬間的な真空状態を作って、その音を際立たせることです。
これはフォルテッシモの表現でも同じことです。(ただし、アクセントとフォルテは意味合いが違う!)
その具体的な手法として、私は直前の音に積極的な消音をおこなうべきと考えます。
なぜ、「積極的な消音」と、私は言うかは、
消音することがエネルギーとなって音楽の進行に推進力を与える目的を意味するからです。
すなわち、鈴木の言う「真空状態」をアクティブにとらえた表現です。
あえて言うなら、「消極的な消音」とは、
流れを妨げ止まりそうな、淀んで詰まったような、雰囲気を重たくさせ、次の音の出を遅らせる、これらの消音です。
もちろん、スタッカートでの消音や、フレーズの中の休符の消音も同じことです。
この積極性の意味するものは、次の項の最初の鈴木の引用文にあります。
2) 空間の表現
音楽がスタートした以上、その曲が終わるまでの間に存在するすべてのものは、
みな音楽の中に生きて存在する重要な要素ばかりである。
そこには、休み、とどまるものは何もないはずである。
と彼は言い、「休止」という日本語の適用が初心者に与える誤解を危惧しています。
つまり、演奏では、気持ちが休み止まってはならないんです。
私は、いわゆる休止は、音を出さずに、エネルギーを蓄積することだと思います。
このことは、私のいう積極的な消音を、休符で楽譜に書かれた場合と思っています。
確かに、休符の前では気持ちが一段落する場合が多いわけですが、観客には一息つかせておいて、
舞台の幕間の裏方では、まるで大忙しの大道具の入れ替えをやっているような緊迫感の内面があります。
しかし、自分まで休んでしまっては舞台進行はお手上げです。
その外面的な休止(聴衆が感じる休止)の感じさせかたは、彼によると、
絵画において空間が重要な役割をもつように、音楽でも極めて重要な分部である、と。
特に日本には、書道、水墨画、庭園、生け花など、空間を同等にバランスで主張する文化が多いことに気づきます。
そして、室内楽などでよくあるゲネラル・パウゼ(1小節全体休符)は、
ひとやすみではなく、ピアニッシモ以下の、人には聞こえない音楽の表現の一部と彼は言い切ります。
いわば、休符を演奏(演出)しなければならないと言えるでしょう。
ただ、ゲネラル・パウゼでは、イン・テンポのままで突入して意表を突く場合が多いようです。
このとき、演奏者は息を止め、今にも爆発しそうな自分をグッと我慢しているように見えるもです。
そして、フレーズの合間の空間について、という重要なテーマですが、
テンポに変化を与える場合と、与えない場合があり、さらに、
休符がある場合、それと休符がないときの下記のような区切り方など。
休符がないとき、音価(音符の長さ)を短くして、残りを休符にする場合。
無音の空間を瞬間意図的にはさんで、時間を歪ませ、しかしそれが感覚的な落ち着きとなる場合。
休符や空間ではなく、イン・テンポ(規定のテンポ)の流れで、物理的空間ではなく、
効果的な音の収束と、空間を作らず、息を瞬間止めるような表現の区切りをつける場合、などを指摘しています。
もし、休符による区切りの場合でも、それは歌唱のように息を吸う「裏方の仕事」があり、休憩ではないんですね。
歌では、その息の吸い方の演奏(音を出さない演奏)が、次のフレーズの表現に大きく影響するわけです。
おおむね、フレーズの区切れでは、ややテンポを落とす方が聞き手を落ち着かせるものです。
重要なことは、フレーズの区切れがわかっていることであり、聞き手にもそれを伝えることです。
「拍子の間」の名人、それは音楽表現の名人であり、すなわち演奏の名人であると、鈴木は
彼が傾倒するチェリスト、カサルスの演奏した「鳥の歌」の譜面を掲げて言っています。
この曲は、カサルスのすべてを象徴するかのような演奏であり、譜面を見ながら、それを聴くとき、
音楽の表現の深さ、イヤむしろ人間の情念の深さの現れを感じ取ることができるものです。
彼がこれを弾くとき、「鳥は空でピース、ピースと鳴いている」と平和をいつも訴えています。
それは、演奏に当たって音符の時間的配分を考えながら弾かれたものではないことは確かなことです。
何度も何度も、心の中で歌い、さまざまに心をよぎる想いがあって、祈りのような情感が自然に
楽器に乗り移ったように、楽音によって蘇り変容するテンポで語られていると言えるでしょう。
私たちが演奏の理想として聞かねばならないのは、フレーズについてのすべての音楽表現です。
もし、自分で弾いてみようとするとき、表現のための運指がいかに大事か、ということにも気づくでしょう。
鈴木は、このことに触れていませんが、我々には大変重要な問題です。
私は、運指に無頓着な人には、音楽表現の意図の有無を疑います。
運指は、単に合理性だけで決められるべきものではないし、
強弱を伴うレガート、音質量とその音色と残響、そして駆使される消音、これらに熟慮して決めるべきです。
また、アクセントや、レガートや、ヴィブラートのかけやすいようにも。
同じ音でも、別の指で押さえなおすことでアクセントが容易になったり、同じ指で移動することでレガートになったり。
これらも何度も試行して運指の上でフレーズ表現を求め、そして、いろんなパターンを用いても良いと思います。
楽譜の中の二重線のスラッシュはフレーズの区切れで、スラーはチェロでのレガートのボウイングを示しています。
(転載楽譜の最後の音は、「ソ」ではなく「ラ」の間違いです)
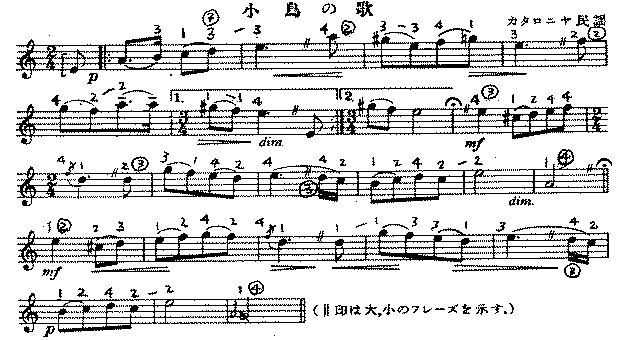
1拍目の「ミ」は吸音(息を吸うような音)で、静かに始めます。
当然、小節最初の「ラ」は呼音(息を吐くような音)で、次の「シ」は軽くして、
次の「ド」とのイレギュラーな運指で、「ド」を際立たせます。そしてフレーズ全体はピアノです。
「ド、レ」はレガートですが、次の「ミ」との間に音の途切れがあってはダメです。
この「ミ」のクレッシェンドは残念ながらギターではできません。
しかし、そのつもりで弾きます。その結果、ヴィブラートをしたくなるはずです。
ただし、痙攣のようなゴリゴリとやるヴィブラートではなく、指のしなりによる優しいウェーブで。
つまり、「ミ」を強めに弾いて、少ししてから、
弦を強く引っ張るようにしてヴィブラートをかけ残響を成長させます。
ほんのわずかな効果ですが。。。
次のフレーズの始まりである「ラ」は、左指をしっかり準備してから、
のっけからヴィブラートをかけて、のびのびと弾きます。
直前に休符はありませんが、このフレーズの切れ目では、息を吸う空白で「ラ」の迫力を出します。
それは、空白を入れると言うよりは、
前の「ミ」をリタルダンドした上で、伸ばしきって消音するという意識です。
なお、次の「ラ」は弱起と思って、弱くはじめないないほうがいいのです。
このフレーズの情感は、大きなため息のクレッシェンドです。
「♯ソ、ミ」は人の声のように、わずかにポルタメントを意図します。(適度にです!)
三つ目のフレーズは、嘆きのフレーズで、詠嘆のあとの「ミ」の収め方がこのフレーズに意味を持たせます。
そして、リピートをした後のフレーズでは、メゾフォルテで、気持ちが少しはやります。
しかし次のフレーズで、悲しみが戻ってきて降下の物憂いメロディになります。
さらに、次のフレーズは、自分に言い聞かせるような刹那さで一旦終わります。
ここで注意することは、
3段目の3小節目の、ひとつのボウイング記号の中に、フレーズの切れ目があることで、
チェロでは、どのように弾かれるのかを想像してみる必要があります。
おそらく、下降する弓が一旦止まって、次の小節に向かって、また動き出すようにするでしょう。
そして16分音符から、次の小節の1拍目の弓の切り替えは、瞬時に鋭くボウイングされるでしょう。
そして4段目の、心の叫びのようなリフレインにメゾフォルテで入ります。
前のメロディと比べると、2回目のものは、四分音符で始まり、音がふたつ多くなって、情感が増幅しています。
だから、1拍目の「ミ」は、豊かにテヌートして、クライマックスを歌います。
そして、同じメロディーで曲を閉じますが、
最後のフレーズは前回のときより弱く、またテンポを弛緩すべきでしょう。
ふたつの連なる二分音符はでは、気持ちを休めずレガートを保ち、収束の表現をします。
いつも、曲の最後の音は、終わりの瞬間を表現するのではなく、曲全体の旅路の思い出を表現します。
(楽譜をクリック)
さて、フレーズとレガートの関係をギターで考えるとき、
ギター練習者にはおなじみの、カルカッシの25の練習曲(Op.60)の第1番や、
ソルの練習曲(Op.6-8、セゴヴィア編の1番)が良い課題かと思います。
これらを音楽にすることは大変難しく、フレーズのアーティキュレーションの検討に耐える曲だと思います。
これらを後回しにしたアマチュアはどれだけ多いことか想像は容易です。私の体験からも。。。
私もやっと、ここまで弾けるようになったかな、という初歩的段階で、手本とはなりません。
カルカッシの曲では、なかなか、ふくらみのあるなめらかなレガートを弾けないのです。
また、ソルの曲では、立体的で、わかりやすく退屈しないお話しに、なかなか聞こえないことです。
音楽として組み立ててゆくとき、いろんな表現パターンのレガートができないといけないことに気づきます。
山あいの細い渓流のような水の流れの変容を表現するために。
しかも、フレーズの区切れになるところでは、次のフレーズとの立体的なコントラストが必要です。
まるで岩の段差を落ちては、そのエネルギーを元に、さらに新しい流れを作り出す水の流れのように。
何度も弾いてみて、ディナーミック(強弱、その音質量変化)、アゴーギク(音質量によるテンポのゆれ)を試行します。
出版楽譜のディナーミック記号などを、
まるで交通法規のように捕らわれていては、その試行の大きな妨げになります。
徐々に視野を広げて、サーキットのコースの全貌を体得してゆくように、
自分の走りをイメージしてゆくことと同じでしょう。
そのためには、今までに書いた事柄、特に鈴木鎮一の啓示をもとに、実際に出来なければなりません。
これでいいだろうか、と迷っているうちはダメで、今の自分の表現はこうだ、と思うまで仕上げないと。
別の機会に弾けば、またちがったイメージで弾くでしょうが、それは人間として当たり前のことであり、
自分の理想のパターンも、形の固定化としてではなく、信念のようなもので姿を変えてゆくでしょう。
信念とはひとつの形ではなくて、細胞の核のようなもので、
それを包む自己表現は、時とともに変容します。
ギターで、フレーズと空間を考える課題として、ソルの練習曲(Op.31-20,セゴヴィア編の9番)を見るなら、
8分音符と8分休符が交互に連続するわけですが、
ここで、スタッカートによる空白と、休符による空白の違いを考えたほうがよいでしょう。
この曲は、4分音符のスタッカートのように、8分音符と8分休符に分けて弾く、テヌートと消音の練習であって、
4分音符の短いスタッカートの練習ではないし、またそう弾かれるなら、なんか追い立てられるような気分になります。
8分音符をしっかりテヌートして(たとえ休符の音価にメリ込んでも)、残響を感jるような休符を演奏するべきです。
大事なことは、次の音を出すタイミングを急がず、正確なテンポを保つことでしょう。
ある出版楽譜で、Tranquillo(静かに、穏やかに)と書いてあるのがありますが、どうも納得できませんね。
もっとも、速く演奏する場合、演奏は4分音符のスタッカートに近づくでしょう。ただしあせってはダメ。
また、ソルの練習曲(セゴヴィア編の11番、15番)には、頻繁に休符が使われています。
前者で気をつけることは、
4/4なのですが、1/4や2/2の拍子に聞こえないような、アクセント対比と空間作りの消音でしょう。
後者では、
1拍目の中の16分休符に惑わされて、あとの8分休符が短くなり、あせった感じにならないことです。
この2曲では、休符を演奏するというよりは、メトロノームの振り替えしの時のような空白を作る練習だと思います。
このように、フレージングを考え、そのイメージのために、あらゆる要素を見出して
アーティキュレーションを永遠に試行することが本来の音楽の練習であることは言うまでもないでしょう。
さて、次に鈴木は、「点の表現」について述べていますが、
これもかなり重要なテーマですので、次回にしたいと思います。
とにかく、フレーズの空間について、鈴木は、
よろしくないのは、フレーズをまったく意識しない演奏で、休符が書かれていないときには、
さらにひどいことになる、というふうに書いています。
もっとよろしくないのは、区切りや休符が意識されていても、節操がなかったり、
気を抜いて休んでいるかのように聞こえてストレスを呼ぶ演奏だと、私は思います。
クラシック音楽の大原則は、肝に銘じたいものです。すなわち、
音楽がスタートした以上、その曲が終わるまでの間に存在するすべてのものは、
みな音楽の中に生きて存在する重要な要素ばかりである。
そこには、休み、とどまるものは何もないはずである。
![]()
談話室 6.
では、ここで、今回のテーマに関連する実践的な課題として、
「ポッポッポ−、ハトポッポ−」と、よくご存知の歌の出だしを、実際にギターで弾いていただけますでしょうか。
そして、あなたの弾き方によって、あなたのアーティキュレーションの体得の度合いを判断してください。
***実習タイム***
さて、あなたの弾き方は、「ポーポーポーハトポ-ポー」とはなりませんでしたか?
消音に一切の意識がなかったとしたら、そうなるでしょう。
もし、そうだった人でも、ギターではなく、リコーダーであれば、そうはならなかったでしょう。
なにも歌詞の歌い方どおりに弾けというわけではないんですが、万人の耳にしみついたこの歌は、
それなりのアーティキュレーションで弾くべきでしょう。
おそらく楽譜は、4/4拍子で、四分音符ではなく、八分音符と八分休符で始まっているでしょう。
たとえ、四分音符で書かれていたとしても、積極的な消音によって、同じように弾くべきです。
いちばんのポイントは、「ポー」の、その1拍の時間のなかで、
どれだけ音を伸ばして、どのように消音するかの一連のタイミングです。
もちろん、次の音との連続的な流れの中で判断しなければなりません。
弾く、それから消音するという二段構えの処理ではなく、ひとつの処理と認識しなければなりません。
ちょうど、カエルがひと飛びするように。あるいは押印するときのように。
そのタイミングは、考えて見計らってされるのではなく、思わず、そうされるものでなければなりません。
それに、大事なのは、そのようなタイミングをうまく実現させるような音質量で、自ずと撥弦されることです。
私は、この消音のしかたの演奏に音楽的センスが凝縮されていると思います。
これは、次の章のテーマ「点の表現」を象徴します。
とにかく、音の弾きっぱなし、フレーズの棒弾きでは、音楽への道は遠いと言わざるを得ません。
ここでは、二つのフレーズがあって、その明確な区切りが必要です。
前半では、三つ目の「ポ」 に向かって盛り上がり、その最後は「ポーッ」
と軽く伸ばし、そしてしっかり休符を取る。
後半は、「ハト」 と「ポッポー」 に分かれ、その間に瞬間的な空白があって、次の「ポ」
を明確にします。
もちろん、「ハト」 は、歌ってみてもわかるように、「ト」
がおのずと弱い響きであることも大事です。
そして最後の「ポー」 は、前半の最後の「ポ」
とは違って、かなり押さえ気味にし、そっと消えるようにして、
次に続く「おはなし」に期待感を持たせる演出をします。
これらの音楽的な配慮は、
弾き手は、常に聞き手の身になって、その受け取り方を意識した話し手であるべきだからです。
余談室 6.
上記の音源の、カルカッシの練習曲の演奏は、お手本にならないものですが、
若い頃、この曲ってほんとに弾けませんでしたね。
独学の私には、解決の糸口が見つけられなかったのです。
ほんとうに良い教本ってなかったですね。今も(?)
結局、アポヤンドや、i , m の交互の固執が妨げになっていたようです。
なかでも、フレーズの最後の音の消音の仕方が、なかなかわかりませんでした。
確かに初心者の練習の過程では、書かれた右指の使い方をすることが、後々のためになるのは必至です。
でも、弾けないままにしておくよりは、出来ることで工夫して音楽にすることも大事だと思います。
なによりも、聞いて気持ちよい音楽になれば、手段は問わないわけですから。
そして、音楽の全体の組み立ても、楽譜に書かれた各種の記号にとらわれず、
自分の感性を磨いて、自分なりに組み立て、人に聞いてもらって意見を言ってもらうことも必要なことです。
音楽を聞く方は、体験的に、良い悪いが自然に判断できるようになるものです。
さらに、何が良いか、何が悪いかを具体的に言える人は、さらに音楽鑑賞体験が深い人といえるでしょう。
そして、音楽を弾く人は、そのレベル以上を目指さなければ、人に聞かせる演奏はできないでしょう。
私の演奏は、残念ながら、そんな理想に程遠く、思ったよりディナーミクの幅は狭くなってしまい、
まるでアンプのパワー不足を感じ、人の耳へは思いが十分伝わらないことを痛感します。
自分なりの表現がある程度掴めても、さらにそれを人に伝えるには、
伝えるための大胆なディナーミクと音色の変化などの「伝達練習」も必要なのだと思うのです。
ところで、ディナーミクは音量(音の強弱)のことですが、それはただ単に音の大きさではないことが、
次の実験でわかると思います。
たとえば、音楽を聞くとき、アンプのボリュームを増減しても、音楽表現の強弱にはなりません。
それは楽器に近づいたか遠のいたかの感じでしかなく、
ボリュームを上げても、フォルテの勢いのある表現にはならないし、また
ボリュームを下げても、ピアノの静かな緊張感の表現には聞こえません。
つまり、ディナーミクは、物理的音量だけではなく、強弱の表現意欲がエネルギーとなる「音質量」なのです。
ソルの練習曲では、フレージングの組み立てがなかなか理解できませんでした。まだ不十分です。
理解できても、実際の演奏に明確に現れないのは、まだわかっていない証拠でしょう。
どうしても近視眼的に見てしまい、全体構成ができていないと聞いて退屈な曲になってしまうわけです。
そして、難しいことに、和声(音の縦の関係)に無頓着だと立体的でない薄ッペライ演奏になることです。
ギターという和声楽器を弾くからには、そのことをおろそかにはできません。
ではまた。。。(2004.3.20.)
![]()